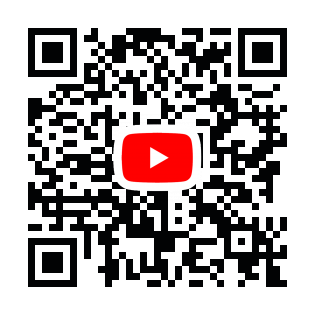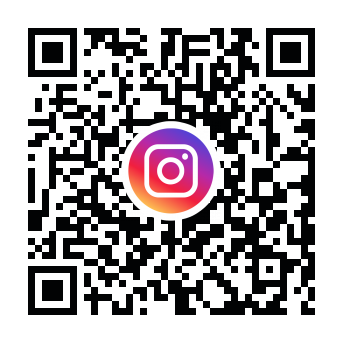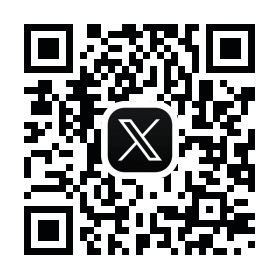沖縄のシュノーケリングで見られるサンゴの種類

生き物の名前を覚えようシリーズ第三弾!
※第一弾のチョウチョウウオ編はこちら!
※第二弾のスズメダイ編はこちら!
サンゴの名前を覚えたいなと思ったので、沖縄の海で出会ったサンゴの名前を調べて一覧にしていくことにしました。
とはいえ何千種もいるサンゴを見分けるのは難しい…。なのでまずは、
「これはミドリイシ科だ!」
「あれはハマサンゴ科だ!」
っていうくらいザックリと見分けられるようになることを目標にしたいと思います。
これは陸の動物で言うと、
「これはネコ科だ!」
「あれはイヌ科だ!」
って分かるのと同じレベルです。
そう考えると出来そうな気がしますよね。
ところでそもそもサンゴって何ものなのでしょうか。 サンゴというのは刺胞動物門というグループに含まれる動物のうち、主に炭酸カルシウムからなる骨を持っている動物の総称です。 刺胞動物門にはクラゲやイソギンチャクも含まれますが、彼らには骨がないのでサンゴではありません。 刺胞動物門の動物はみんな刺胞という毒針細胞を持っているのが特徴です。
サンゴには外骨格という大きな骨をもつ種類と、骨片という小さな骨のかけらを持つ種類がいます。 外骨格を持つサンゴは硬いのでハードコーラル、骨片を持つサンゴは柔らかいのでソフトコーラルと呼ばれています。
またサンゴには褐虫藻という藻類と共生している種類と、共生していない種類があります。 褐虫藻と共生しているサンゴは有藻性のサンゴ、共生していないサンゴは無藻性のサンゴと呼ばれています。
ちなみに有藻性のハードコーラルはサンゴ礁を作るので造礁サンゴとも呼ばれています。
以下に目次も兼ねて、サンゴの生物学的な分類を載せておきます。
刺胞動物門
┃
┣ポリポジオゾア綱(寄生性のクラゲ)
┃
┣十文字クラゲ綱(海底生活するクラゲ)
┃
┣箱虫綱(ハブクラゲなど)
┃
┣鉢虫綱(ミズクラゲなど)
┃
┣花虫綱
┃ ┃
┃ ┣六放サンゴ亜綱
┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣イソギンチャク目
┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┗イシサンゴ目
┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣ミドリイシ科
┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣ハナヤサイサンゴ科
┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣ハマサンゴ科
┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣クサビライシ科
┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣サザナミサンゴ科
┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣ヒラフキサンゴ科
┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣ダイオウサンゴ科
┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣オオトゲサンゴ科
┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣キサンゴ科
┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┗ハナサンゴ科
┃ ┃
┃ ┗八放サンゴ亜綱
┃ ┃
┃ ┣Scleralcyonacea目
┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┗アオサンゴ科
┃ ┃
┃ ┗Malacalcyonacea目
┃ ┃
┃ ┣イソバナ科
┃ ┃
┃ ┣チヂミトサカ科
┃ ┃
┃ ┗ウミトサカ科
┃
┗ヒドロ虫綱
┃
┣花クラゲ目
┃ ┃
┃ ┗アナサンゴモドキ科
┃
┗管クラゲ目(カツオノエボシなど)
※すべてを網羅しているわけではありません。
※一部簡略化している部分もあります。
※生物の分類には現在でも様々な学説があり、上のグラフはあくまで一説です。
※八放サンゴ亜綱やサザナミサンゴ科は大きな改編があったので、古い図鑑などで調べるときは注意が必要です。
※Scleralcyonacea目とMalacalcyonacea目はまだ和名がありません。
ミドリイシ科(Acroporidae)
ミドリイシ科には、ミドリイシ属(Acropora)やコモンサンゴ属(Montipora)、アナサンゴ属(Astreopora)などがあります。 テーブル状、枝状などの定番の形のほか、指状や葉状、塊状、被覆状など形もバリエーション豊かです。
ミドリイシ科の中で最も人気があるのは、何といってものミドリイシ属のサンゴだと思います。 テーブル状や枝状など、形や色が華やかな種が多いのも特徴です。 人気のサンゴなので、ミドリイシ属のサンゴだけを種別に紹介した別記事もいつか作れたら良いなって思っています。

テーブル状のミドリイシ属サンゴにはハナバチミドリイシ(A. cytherea)やクシハダミドリイシ(A. hyacinthus)などがあります。 次の写真のように直径1mを超えるものも珍しくありません。

テーブル状のサンゴは下の写真のように、リーフエッジの斜面に沿って生息していることが多い気がします。

枝状のミドリイシ属サンゴにはスギノキミドリイシ(A. muricata)やトゲスギミドリイシ(A. intermedia)などがあります。

枝状のミドリイシ属サンゴはリーフエッジよりも少し内側に生息していることが多い気がします。

ミドリイシ属サンゴには、下の写真のような指状のものもあります。 指状のミドリイシにはオヤユビミドリイシ(A. gemmifera)やコユビミドリイシ(A. digitifera)などがあります。

ミドリイシ科のサンゴのもうひとつの代表はコモンサンゴ属サンゴです。 下の写真に写っている枝状のサンゴは、リーフ内でとてもよく見かけるエダコモンサンゴ(M. digitata)です。 キャベツのような形の葉状のサンゴの方は、ウスコモンサンゴ(M. foliosa)かチヂミウスコモンサンゴ(M. aequituberculata)です。

ウスコモンサンゴやチヂミウスコモンサンゴのことを、リュウキュウキッカサンゴ(サザナミサンゴ科)だと誤解している人がとても多いです。 見分け方はMaoさんの動画で詳しく解説されています。
ハナヤサイサンゴ科(Pocilloporidae)
ハナヤサイサンゴ科には、ハナヤサイサンゴ属(Pocillopora)、ショウガサンゴ属(Stylophora)、トゲサンゴ属(Seriatopora)などがあります。
ハナヤサイサンゴ科の中で人気のサンゴは、下の写真のハナヤサイサンゴ属のサンゴだと思います。

下の写真はたぶんショウガサンゴ属のサンゴだと思います。

ハマサンゴ科(Poritidae)
ハマサンゴ科には、ハマサンゴ属(Porites )やハナガササンゴ属(Goniopora )などがあります。
ハマサンゴ科のサンゴといえばハマサンゴ属のサンゴたちだと思います。 全長数m以上にもなる巨大な群体を作るサンゴです。 中でも人気のサンゴはユビエダハマサンゴ(P. cylindrica )という、下の写真にある枝状のサンゴです。

下の写真のようなユニークな形をしたパラオハマサンゴ(P. rus )も人気です。

下の写真はたぶんフカアナハマサンゴ(P. lobata )です。 沖縄本島の大浦湾にある、直径10m近い群体です。

その他のほとんどのハマサンゴは似たような塊状のものが多く、見分けるのは難しいです。

塊状のハマサンゴは微環礁(マイクロアトール)を作ることでも有名です。 下の写真は瀬底島の南にある直径10m弱の巨大な微環礁です。

下の写真はたぶんハナガササンゴ属のサンゴです。 ハナガササンゴのポリプはとても長く伸びていて、一見するとソフトコーラルのようにも見えます。

クサビライシ科(Fungiidae)
クサビライシ科には、マンジュウイシ属(Cycloseris )、カワラサンゴ属(Lithophyllon )、カブトサンゴ属(Halomitra)などなどがあります。 ですが、どれも似たような楕円形をしていて、種を見分けるのはもちろん、属を見分けるのもなかなか難しいです…。
クサビライシ科のサンゴの特徴は2つあります。 ひとつ目は個体(単体のポリプ)で生活していることです。 ほとんどのサンゴがたくさんのポリプが集まってひとつの群体を作っているのに対して、クサビライシ科のサンゴは大きなひとつの個体で生活しています。
ふたつ目は岩などに固定されていないことです。 若い頃はマッシュルームのような形で固定されているのですが、成長すると根っこから外れ、明るいところを求めて秒速2cmくらいで移動します。

サザナミサンゴ科(Merulinidae)
サザナミサンゴ科には、キクメイシ属(Dipsastraea)、リュウキュウキッカサンゴ属(Echinopora)、ノウサンゴ属(Platygyra)、ウミバラ属(Physophyllia)、 サザナミサンゴ属(Merulina)、コカメノキクメイシ属(Goniastrea)、タバネサンゴ属(Caulastraea)などがあります。
下の写真はたぶんノウサンゴ属のサンゴです。

下の写真はたぶんウミバラ属のサンゴです。

下の写真はたぶんカメノコキクメイシ属のサンゴです。

下の写真はたぶんキクメイシ属のサンゴです。

下の写真はたぶんタバネサンゴ属のサンゴです。

下の写真は鳩間島にあるリュウキュウキッカサンゴ属のサンゴの群生です。

※キクメイシと呼ばれているサンゴの分類は最近大きく変わったので、古い文献を調べるときには注意が必要です。 昔はキクメイシ科(Faviidae)というグループがありましたが、これは解体されて、多くはサザナミサンゴ科に吸収されました。 また太平洋に生息するキクメイシ属の学名はFaviaからDipsastraeaに変更されました。
ヒラフキサンゴ科(Agariciidae)
ヒラフキサンゴ科には、シコロサンゴ属(Pavona )やセンベイサンゴ属(Leptoseris )やリュウモンサンゴ属(Pachyseris)などがあります。
下の写真はたぶんシコロサンゴ属のサンゴだと思います。 リーフ内でよく見かけます。

シコロサンゴ属のサンゴで特に人気なのは、下の写真のコモンシコロサンゴ(P. clavus)だと思います。 数mを超える巨大な群体を作ることもあります。 下の写真は瀬底島にある直径5mくらいの群体です。

下の写真はたぶんリュウモンサンゴ属のサンゴだと思います。

ダイオウサンゴ科(Diploastreidae)
ダイオウサンゴ科に含まれるのはダイオウサンゴ属(Diploastrea)のダイオウサンゴ(D. heliopola)だけです。
数m以上の群体を作ることもある巨大なサンゴで、見た目も分かりやすいので、見分けやすいサンゴです。 わりとメジャーなサンゴです。

オオトゲサンゴ科(Lobophyllidae)
オオトゲサンゴ科には、ダイノウサンゴ属(Symphyllia)、ハナガタサンゴ属(Lobophyllia)、アザミハナガタサンゴ属(Scolymia vitiensis)などがあります。
下の写真はたぶんダイノウサンゴ属のサンゴです。

下の写真はたぶんハナガタサンゴ属のサンゴです。

下の写真はたぶんアザミハナガタサンゴ属のサンゴです。 単体の大きなポリプから成るのが特徴です。

キサンゴ科(Dendrophylliidae)
キサンゴ科のサンゴとえばスリバチサンゴ属(Turbinaria)だと思います。
下の写真はたぶんスリバチサンゴ属のサンゴです。 スリバチサンゴ属のサンゴはポリプの間隔が広いのが特徴です。

ハナサンゴ科(Euphylliidae)
ハナサンゴ科には、アザミサンゴ属(Galaxea )やナガレハナサンゴ属(Euphyllia )などがあります。
下の写真はアザミサンゴ属のサンゴです。 アザミサンゴ属のサンゴは昼間でもポリプをよく伸ばしていて、そのポリプが銀河のように見えるのでギャラクシーコーラルとも呼ばれています。 10cmくらいの群体が多いですが、ポリプが赤、青、黄、緑などとにかくカラフルでとっても綺麗なサンゴです。

アオサンゴ科(Helioporidae)
これまで紹介したサンゴはすべて、六放サンゴ亜綱というグループのサンゴでした。 ここからはしばらく八放サンゴ亜綱というグループのサンゴになります。 八放サンゴ亜綱のサンゴはほとんどがソフトコーラルなんですが、ここで紹介するアオサンゴ科のサンゴはハードコーラルです。
アオサンゴ科の代表はアオサンゴ属(Heliopola)のアオサンゴ(H. coerulea)です。 下の写真は沖縄本島の大浦湾にある、直径10mを超えるアオサンゴです。 ここまで大きな群体は珍しいですが、直径1m前後の群体は結構いろんな場所で見かけます。

触手が長いので、触手が伸びている部分は雪が積もったように白くなっていてとても綺麗です。

六放サンゴ亜綱のサンゴは骨格が白いのに対して、アオサンゴの骨格は青いのが特徴です。

※上の写真は自然に折れていたものを撮影したものです。
イソバナ科(Melithaeidae)
イソバナ科のサンゴで人気なのはイソバナ属(Melithaea )のサンゴだと思います。

沖縄本島でイソバナがたくさん見れるのは知名崎が有名です。
チヂミトサカ科(Nephtheidae)
チヂミトサカ科のサンゴといえばトゲトサカ属(Dendronephthya )だと思います。
トゲトサカ属のサンゴはソフトコーラルで、他のソフトコーラルと比べて骨片が表面の近くに多いのが特徴です。

ウミトサカ科(Alcyoniidae)
ウミトサカ科には、ウミトサカ属(Alcyonium )、ウネタケ属(Lobophytum )、ウミキノコ属(Sarcophyton )、カタトサカ属(Sinularia )などがあります。
下の写真はたぶんウネタケ属のサンゴです。

触手を出してない時は下の写真のような姿をしています。

下の写真はたぶんウミキノコ属のサンゴです。

触手を出してない時は下の写真のような姿をしています。

下の写真はたぶんカタトサカ属のサンゴです。

ウミトサカ科のサンゴは、沖縄本島では砂辺でよく見られます。
アナサンゴモドキ科(Milleporidae)
これまでに紹介したサンゴは、ハードコーラルもソフトコーラルもすべて、花虫綱という大きなグループのサンゴでした。 最後に紹介するアナサンゴモドキ科のサンゴは、ヒドロ虫綱という全く別の大きなグループのサンゴになります。 ヒドロ虫綱には、あの有名な危険生物「カツオノエボシ」なども含まれています。
アナサンゴモドキ科に含まれるのはアナサンゴモドキ属(Millepora )だけです。
アナサンゴモドキ科のサンゴは枝状で半球状の群体を作るものが多いです。 下の写真はたぶんヤツデアナサンゴモドキ(M. tenella)だと思います。

また被覆状の部分から板が立ってるような形の群体もよく見かけます。 下の写真はたぶんイタアナサンゴモドキ(M. platyphylla)だと思います。

アナサンゴモドキ科のサンゴの刺胞には強い毒があって、刺されると火傷したように痛いので「ファイヤーコーラル」とも呼ばれています。 アナサンゴモドキ科のサンゴは、ポリプが肉眼では見えないほど小さいのも特徴です。
参考
今回サンゴについて色々と調べてみて、サンゴってグループ分けするだけでもこんなに奥が深いんだなって思いました。 私たちは専門家ではないので、間違った情報を載せてしまっているかもしれません。 サンゴに興味のある方はぜひ一度、サンゴ博士MaoさんのSNSを覗いてみて下さい。 より正確な情報がとても分かりやすく発信されています。
その他、私たちが参考にしている情報はこちら。
- 山城秀之『サンゴ 知られざる世界』
- 西平守孝『造礁サンゴ(フィールド図鑑)』
- 屋比久壮実『磯の生き物:沖縄のサンゴ礁を楽しむ(おきなわフィールドブック2)』
- https://www.nies.go.jp/tanegashima/sango_db/profile.cgi
- https://coralmonogr.jpn.org/index.html
- https://www.godac.jamstec.go.jp/bismal/j/
- https://churaumi.okinawa/sp/fishbook/
- https://rismi.web.fc2.com/index.html
- https://ujssb.org/index.html
- https://www.marinespecies.org/index.php
Follow Hitoiki