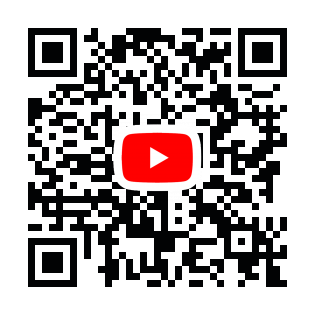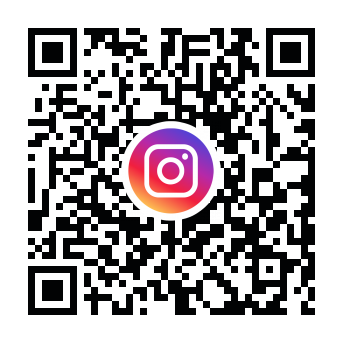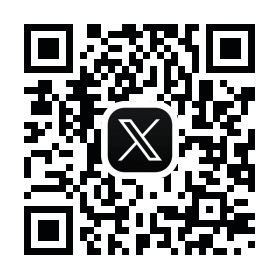沖縄のシュノーケリングで見られるクマノミの種類と生態

シュノーケリングでもダイビングでも大人気のクマノミ達。 ディズニー映画「ファインディングニモ」のおかげか、海には潜らない人にも人気のお魚です。 彼らの種類や生態についてまとめてみました。
クマノミとは
ひとまとめに「クマノミ」と言いますが、一般的にクマノミと呼ばれているのは、スズキ目スズメダイ科クマノミ亜科に属するお魚達です。 クマノミは全世界では30種くらいいますが、そのうち日本の海で会えるのは次の6種です。
- カクレクマノミ
- ハナビラクマノミ
- ハマクマノミ
- トウアカクマノミ
- セジロクマノミ
- クマノミ
クマノミは暖かい海のイソギンチャクに住んでいます。 イソギンチャク(anemone)に住んでいるので、英語ではanemonefishと呼ばれたり、ピエロ(clown)みたいな動きをするのでclownfishと呼ばれたりもします。
カクレクマノミ(ocellaris clownfish)

カクレクマノミ(学名:Amphiprion ocellaris)はニモでお馴染みの、たぶん一番人気のクマノミで、ほんとに可愛いです。
カクレクマノミが住んでいるイソギンチャクは主にハタゴイソギンチャク(学名:Stichodactyla gigantea)やセンジュイソギンチャク(学名:Heteractis magnifica)です。 下の写真のように触手が短めで浅瀬に多いのがハタゴイソギンチャクです。

下の写真のように触手が長めで深場に多いのがセンジュイソギンチャクです。

センジュイソギンチャクは下の写真のように丸まっていることもあります。

カクレクマノミは沖縄本島では割とどこでも会えますが、 ナカユクイや山田ポイントに行くと特にたくさん見られます。
ハナビラクマノミ(pink skunk clownfish)

ハナビラクマノミ(学名:Amphiprion perideraion)もよく見るクマノミのひとつです。 セジロクマノミに似ていますが、セジロクマノミと違って目の横に白い線が入っているのが特徴です。 またセジロクマノミがオレンジ寄りの色なのに対して、ハナビラクマノミはピンク寄りの色をしています。
ハナビラクマノミが住んでいるイソギンチャクは主にシライトイソギンチャク(学名:Heteractis crispa)という、もやしみたいなイソギンチャクです。
ハマクマノミ(tomato clownfish)

ハマクマノミ(学名:Amphiprion frenatus)もよく見るクマノミのひとつです。 ハマクマノミが住んでいるイソギンチャクは主にタマイタダキイソギンチャク(学名:Entacmaea quadricolor)です。
タマイタダキイソギンチャクは下の写真のように一箇所に集団で生息することがあるので、ハマクマノミも集団で見かけることが多いです。 ハマクマ団地、ハマクマンションなどと呼ばれています。

トウアカクマノミ(saddleback clownfish)

トウアカクマノミ(学名:Amphiprion polymnus)は比較的レアなクマノミです。 トウアカクマノミが住んでいるイソギンチャクは主にイボハタゴイソギンチャク(学名:Stichodactyla haddoni)です。 イボハタゴイソギンチャクは砂地にポツンと住んでることが多いので、トウアカクマノミに出会えるのも基本的には砂地です。
トウアカクマノミの柄は上から見ると下の写真のようにハート柄になっていて可愛いです。

トウアカクマノミは沖縄本島ではナカユクイや石切で見られます。
セジロクマノミ(orange skunk clownfish)

セジロクマノミ(学名:Amphiprion sandaracinos)もレアなクマノミです。 セジロクマノミが住んでいるのはアラビアハタゴイソギンチャク(学名Stichodactyla mertensi)です。 短めの触手が特徴のイソギンチャクです。
ハナビラクマノミに似ていますが、セジロクマノミはオレンジ色なのでサーモンの切り身に似ていて美味しそうです。
セジロクマノミは沖縄本島ではナカユクイや山田ポイントで見られます。
クマノミ(yellowtail clownfish)

クマノミ(学名:Amphiprion clarkii)という名前のクマノミです。 このクマノミがよく住んでいるイソギンチャクはシライトインチャクやサンゴイソギンチャク(学名Entacmaea quadricolor)やジュズダマイソギンチャク(学名:Heteractis aurora)です。 下の写真はジュズダマイソギンチャクに住んでいるクマノミです。

イチハマ、ニクマ、サンカクレ
メジャーな3種(ハマクマノミ、クマノミ、カクレクマノミ)は白い横線の数に注目すると簡単に見分けられます。 ハマクマノミは1本、クマノミは2本、カクレクマノミは3本の線が入っています。 なので「イチハマ、ニクマ、サンカクレ」というキャッチフレーズで覚えている人が多いです。
ただしクマノミの幼魚は3本線に見えるので、カクレクマノミと見間違えやすいです。 カクレクマノミの方が胸ビレが丸く、住んでるイソギンチャクも違うので注意して観察してみて下さい。
クマノミの共生

クマノミの特徴のひとつはイソギンチャクとの「共生」です。 共生というのは複数の種の生き物が同じ場所で生活することです。
共生にもいろんな種類がありますが、クマノミとイソギンチャクは「相利共生」という共生をしています。 相利共生というのはお互いにメリットを与え合っている共生のことです。
クマノミ側のメリットは主に次の4つです。
- イソギンチャクの毒のおかげでクマノミは外敵から守ってもらえる。
- イソギンチャクの周りにはクマノミの餌が集まってくる。
- イソギンチャクの近くに産卵すると安全に孵化できる。
- イソギンチャクに付いたゴミや寄生虫をクマノミが食べられる。
逆にイソギンチャク側のメリットは次の3つです。
- イソギンチャクの捕食者をクマノミが追い払ってくれる。
- クマノミの食べ残しや排泄物をイソギンチャクが食べられる。
- クマノミが泳ぐと新鮮な海水がイソギンチャクに供給される。
イソギンチャクの刺胞には毒があるので、普通の魚は近づくことができません。 でもクマノミは、イソギンチャクが出す粘液に似た粘液を出すことができます。 その結果、クマノミはイソギンチャクに敵認定されず共生することができます。
クマノミの性転換

クマノミのもうひとつの特徴は「性転換」です。
子供のクマノミは両性生殖腺というものを持っていて、オスでもメスでもありません。 そして同じイソギンチャクに住んでいる群れの中で、一番大きな個体がメスに、二番目に大きな個体がオスになります。
そしてもしメスが居なくなってしまった場合は、オスのホルモンバランスが変化してメスに性転換し、群れの中で二番目に大きな個体がオスになります。
これは限られた数のイソギンチャクの中で、効率よく子孫を残すためだと考えられています。 ちなみに同じイソギンチャクに住んでいるクマノミの群れは、家族みたいに見えますが、基本的に血の繋がっていない他人同士です。
参考
- 加藤昌一『海水魚 (ネイチャーウォッチングガイドブック)』
- 大方洋二『クマノミとサンゴの海の魚たち (ちしきのぽけっと5)』
- 屋比久壮実『磯の生き物: 沖縄のサンゴ礁を楽しむ』
- https://t-aquagarden.com/column/ocellaris
- https://marinediving.com/marine_life/fishbook/no01/
- https://www.marinelassic.aqualassic.com/super_clownfish_pictorial/
- https://lapice.biz/guide/okinawa/36602/
- https://oceana.ne.jp/marine-life/141784
- https://www.wwf.or.jp/staffblog/activity/4375.html
- https://onlineshop.sunshinecity.jp/blog/post-1677/
Follow Hitoiki